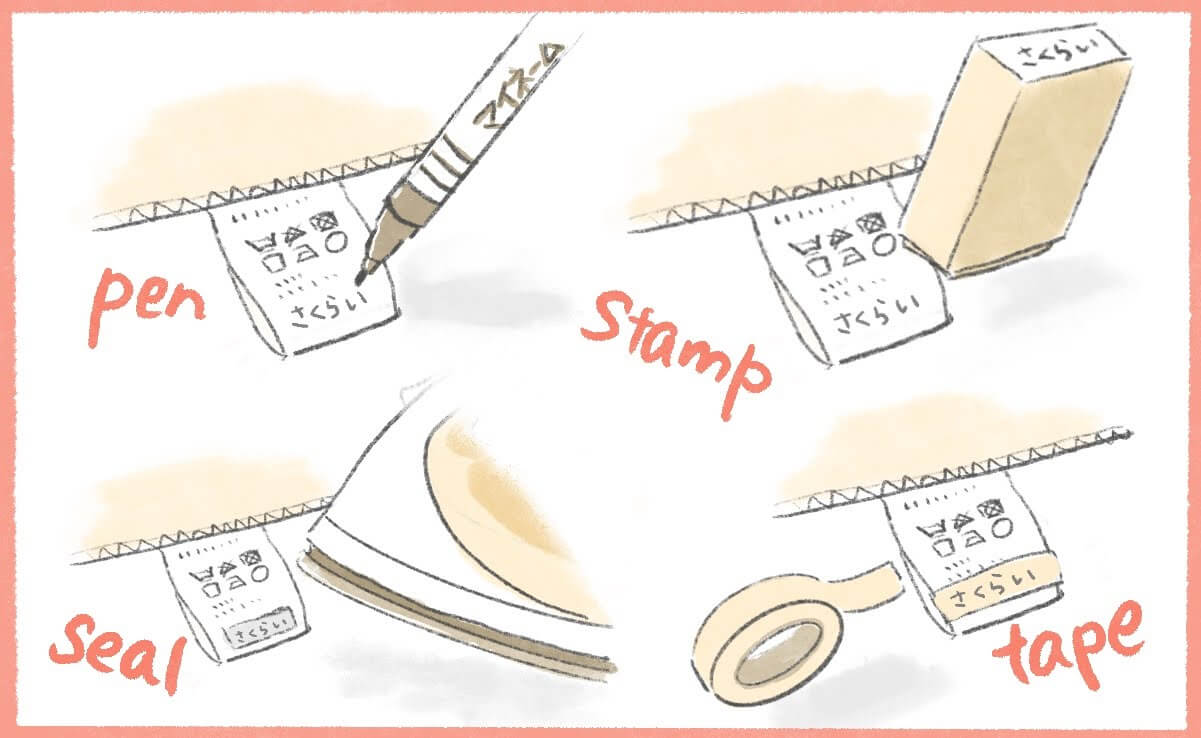NICUとGCUに双子が入院していた話【搾乳便利グッズ・入院生活】

双子は生まれた翌日からNICUとGCUに入院しました。
実はこの時期が、産後の辛い記憶として心に残っています。
思い出をあまり消化できていないなーと思ったので、当時のことを振り返りながら、どうすればよかったのか?を考えて記事にしてみます。
長くなるので、以下の2記事に分けます!
- 入院生活がどんなものだったか、役立ったものをまとめた記事(本記事)
- えまのGCUでの思い出を振り返った記事
特にいま同じようにNICUまたはGCUに赤ちゃんがいるお父さん・お母さんの参考になれば嬉しいです。
NICUとGCUについて
えま家の双子が入院していた病院のNICU, GCUについてお話しします。
病院によって違いはあると思いますが、だいたい似た感じのはず。
NICU(新生児集中治療室)とは
NICUには早産児や何らかの病気を持っている赤ちゃんなど、治療を必要としている赤ちゃんが入院しています。
赤ちゃんには心拍などを計測する機器などが取り付けられていて、医師や看護師さんが24時間体制で赤ちゃんの様子をみてくださいます。
赤ちゃんに刺激を与えすぎないよう、照明は控えめ。
たまにふにゃふにゃとした赤ちゃんの鳴き声が聞こえますが、モニター音がよく響く静かな場所でした。
GCU(新生児回復室)とは
NICUでの治療をへて体調の安定してきた赤ちゃんは、退院に備えてGCUへ移動してきます。
双子が入院していたGCUでは、大きな窓から自然光が入るようになっていて、NICUに比べると明るい場所でした。
赤ちゃんがたくさん入院しているので、赤ちゃんの泣き声がそこかしこから聞こえて活気がありました。
両親は24時間入室可能
NICUとGCUは24時間開いているので、赤ちゃんの両親はいつでも面会にいけました。
日中の面会はもちろん、産後の入院中は朝早くからお世話しに行ったり、夫が仕事帰りに病院へ寄ってミルクをあげることもできました。
ただし両親以外の面会は制限されています。
双子が入院していたNICUでは、子にとっての祖父母が面会可能。
GCUは祖父母にくわえて子のきょうだいが面会可能でした。
いずれも事前予約が必要なうえ、赤ちゃんに負担をかけないよう面会時間も限られていました。
衛生管理が徹底されている
抵抗力の低い新生児を守るため、衛生管理は徹底されていました。
来訪者は入室する前に体調チェックの紙に当日の体調を記入して、少しでも体調不良や発熱があれば入室できません。
入室時に当然手指の洗浄をおこないますが、液体せっけんでの洗浄に加えてアルコール消毒もおこなうという徹底ぶりでした。
双子の入院について、具体的なこと
入院するまでの経緯
ふたりは36週4日で生まれました。
ありがたいことに比較的お腹の中にいてくれたほうだと思いますし、出生体重もふたりとも2300gを超えていましたが、早産のため哺乳力や体温調節機能が弱い状態でした。
特に産後すぐはミルクをなかなか飲めないせいで血糖値が上がらず、低血糖になっていました。
低血糖のままでいると脳に深刻なダメージがあるそうで、出産翌日からNICUに入院することに。
自力で哺乳できて血糖値が安定し、体重が増加する軌道にのるまでみていただくことになりました。

双子の出産前、子どもたちの体重は十分あるし、一緒に退院できるだろうとわたしは思っていました。
そのため母子同室もできないまま入院となったことが予想外の出来事で、動揺して看護師さんの前で泣いてしまったり。
後から看護師さんからうかがったのですが、多胎児の場合、単胎児よりも母体での成長が2週ほど遅いといわれているそうです。
早産になった場合、身体機能が未熟なために入院となるのは、多胎児にはよくあることだそう。
自分を責める必要は全くなかったと、今なら思います。
入院していた期間
双子は、出産翌日(36週5日にあたる日)から、出産予定日だった日の翌日まで入院していました。
出産予定日付近が退院の目安になるそうです。
かかった入院費用
3週前後の入院で、ふたりあわせて10万円程度でした。
自治体の子ども医療費助成があったので、保険適用の治療費はかなりお安くすみました。
自治体や医療機関によってはもっとお安くなるようなので、詳しくは病院の会計窓口などで尋ねてみると良いと思います。
ふたりのお世話をするため、NICU, GCUに通院する毎日
母親は搾乳が生活の中心に
母親であるわたしの大きな仕事のひとつが、入院しているふたりに母乳を届けること。
特に産後1週間に分泌する初乳は赤ちゃんの免疫力を上げる成分が入っているそうで、産後の入院中から必死に搾乳して、NICUの双子に届けました。
退院後は冷凍した母乳を病院へ持っていきます。
母乳の分泌量を維持するため、昼も夜も3時間ごとの搾乳… NICU入院児の母あるあるだと思いますが、生活が通院と搾乳を中心に回っていて、母乳バッグを大量消費していました😅
特にわたしの胸は乳腺が詰まりやすかったので、乳腺炎防止のためにも搾乳は欠かせませんでした。
通院して授乳やオムツ替えなどお世話をする
NICUやGCUでは、授乳の時間になると赤ちゃんに直接母乳をあげる練習をします。
授乳の前後で体重を測り、赤ちゃんがどれくらい母乳を飲めたか推測して、足りない分を搾乳またはミルクで赤ちゃんに与えていました。
この作業が徐々に自分を追い詰めることになるのですが、その話はまた別記事で…。
ほかにも、オムツ替えや体温測定、退院が近づく頃には沐浴の練習など、赤ちゃんとの生活に備えてお世話をおこないました。
産褥期のため、通院はタクシーで
家から病院まで徒歩15分程度だったので歩いて通うつもりでしたが、その話をしたNICUの看護師さんに「産後の体は自分が思っているよりも弱っているから、徒歩は絶対にダメ!」と強く止められ断念。通院にはタクシーを利用しました。
手配の手間はありましたが、後々の自分の体調の変化などを考えると、タクシー利用でよかったと思います。(止めてくださってありがとうNICUの看護師さん…)
産後間もない時期に通院される方は、決して無理なさらないでくださいね…!
1日のルーティン
次のような流れでした。合間に3時間ごとの搾乳があります。
- お昼頃に病院へ着くよう家を出る
- 病院で双子の授乳、お世話
- 授乳室でも搾乳
- 夕方に病院を出る
- 家に着くとどっと疲れが出て、倒れるように寝る
通院生活で役立った搾乳グッズ・アプリ
搾乳にはピジョンの電動搾乳器を使用
借り物のピジョンの片胸用の電動搾乳器をひとつ持っていたので、通院生活が始まってから同じものをもうひとつ買い足し、両胸で同時に搾乳できるようにしていました。
かなり邪道な使い方ですが、とにかく少しでも効率化したかったので…。
搾乳器を持ちながら片手だけでダイヤルを回すことができるので、搾乳しながら強度を調整できてでした。
もし入院が長引くとわかっていて、母乳の分泌が良いのであれば、多少高額でも両胸用を買うのがおすすめです。
わたしのように片胸用×2を使うよりは、ひとつのコントローラで両胸の強度を調整できるので、絶対に便利なはずです。
搾乳にかける時間を節約して、その間は休んでください!
ちなみに、NICUの授乳室にあったメデラのシンフォニーはレンタルもできるみたいです。
さく乳器レンタルのご案内 | Medela (メデラ) 公式オンラインショップ | 母乳育児用品の通販サイト
消毒にはミルトンなどの消毒液がおすすめ
搾乳器はパーツが多く、毎回の洗浄や消毒がとにかく手間でした。
消毒方法はレンジ消毒や煮沸消毒などいろいろありますが、わたしはミルトンなどの消毒液につけておくだけの形が一番楽でした。
1日1回だけ消毒液を取り替えて、あとは洗浄したものを消毒液につけておくだけ。
すぐに次の搾乳の時間がくるので、それまで放置していました。
ミルトンのほか、チュチュベビーが安かったのでよく使っていました。
ちなみに哺乳瓶などの洗浄には、食器用洗剤を使用。
はじめは哺乳瓶専用の洗剤を使っていましたが、GCUで食器用洗剤を使っていると知ってからは変えました。
洗剤が残らないようにすすぎをしっかりとおこない、水をきちんと切っていれば問題ないと思います。
母乳バッグはカネソンかピジョン
搾乳を保存する母乳バッグも必需品です。
えまは主にカネソンの母乳バッグを使用していました。
理由は単純で、産後の入院中に助産師さんからいただいた母乳バッグがカネソンだったから。
密封口が粘着式でしっかりしていて漏れる心配がなく、使いやすかったです。
ピジョンの母乳バッグはカネソンより安価。
密封口はカネソンと違い、ジップロックのような形です。
双子が大きくなり搾乳量が減ってきてから使い始めましたが、特に問題なく使用できたので、最初からピジョンでもよかったかも…と思いました。
タクシー配車アプリ
通院の時に使用していました。
出産前にタクシーで通院する際、タクシー会社に電話をかけても繋がらず、配車アプリを使用したことがきっかけ。
えまが住んでいるのはいわゆる都市部のベッドタウンといった位置付けにある自治体で、タクシー会社の選択肢も比較的あり、アプリならすぐにタクシーが掴まりました。
ただ、地図で指定した場所にタクシーが来ないということが何度かあり(タクシー会社が使用している地図がアプリと異なることが原因だと思います🤔)。
結局、配車アプリで利用して印象の良かったタクシー会社に直接電話して、利用することが増えました。
まとめ
入院生活を書きつづっているだけで長くなってしまいました…。
えまの通院の思い出と、当時どうすれば良かったのかという振り返りは、次の【思い出編】で書きます!

追記:NICU入院中の体験レポを電子書籍化
出産レポとNICU入院中のことを電子書籍にまとめています。よろしければご覧ください!

にほんブログ村